
大井川西俣源流部を巡る 南アルプス 大井川西俣三伏沢~中俣~小西俣内無沢
2024/9/13(金)~2024/9/15(日)
僕は北アルプスより南アルプスのほうが好きだ。北アルプスの人を寄せ付けない陰険な老人のような尖った雰囲気と異なり、南アルプスは優しく僕を抱きとめてくれる嫋やかな女神のようだ。決して北アルプスが嫌いとか、そういうわけではない。あくまで個人的な印象である。
南アルプスといえば大井川である。大井川の源流は、荒れ狂う激流に姿を変えることはほとんどなく、南アルプスの中央部を、微笑みを携えてただゆったりと流れている。女神様に暖かな微笑みを投げかけてほしくて、南アルプスのど真ん中へ向かうことにした。
鳥倉のゲートに着くと、まだ金曜日の朝だというのにほぼ満車状態だった。今日は三連休前の平日だから、やはり皆長く山に入りたいのだろうか。最後の一個だったであろう駐車スペースに車をねじ込み、鳥倉登山口まで退屈なアスファルトを歩いていく。

鳥倉登山口から三伏峠までの標高差700mくらいのトレイルを、身体中の血液を巡らせながらゆっくりと歩いていく。苔に覆われたシラビソのしっとりとした森が続く。なんとも南アルプスらしい雰囲気だ。シラビソの幹をちょこちょこと動き回りながらリスが木登りをしている。木漏れ日の登山道をコツコツと標高を上げていくと三伏峠に着いた。三伏峠小屋はどうやらカレーが有名らしく、「ラジオで聞いて食べに来たよ」という登山客の会話を聞き、帰りに立ち寄って食べられたらいいな、と楽観的に考える。前夜は大鹿村の駐車場でアスファルトに3-4時間寝そべった程度だったので、小屋の前で休憩していると強烈な眠気が襲ってきて、30分程度仮眠してから動き始めることにした。寝ぼけまなこを擦って半分くらい起きれば、さあ、微笑みの大井川へ出発である。


まずは三伏沢を下降して中俣との出合を目指す。三伏沢の源頭部は両岸にシラビソの森が連なる苔むした沢状地形で、霧に隠れた塩見岳の稜線も相まって水墨画のようだ。次第に沢形が広がり、伏流していた沢の流れが目に見えるようになり、足元が苔から礫に変わると次第に魚影も出てくる。中俣との中間あたりまで来ると塩見岳の稜線を覆っていたガスも晴れてきて、塩見岳の山頂部を見ながら軽快に標高を下げていく。


三伏峠から一時間半程度で中俣との出合に着いた。この出合でのんびり大休止を取った。ここから塩見沢の出合まではものの数分だ。塩見沢の出合から30分程度下った右岸に良い感じの幕営適地を見つけ、ここで幕を張ることにした。


目が覚めるとまだ日の出前で、段々と黎明の空に変わっていく。朝食を取り、6時過ぎに出発する。
軽快に進んでいくと、左岸側からとんでもない崩落地形と共に凄まじい量の岩石が中俣に流入し、沢を覆いつくしているではないか。ここが東池ノ沢の出合だ。塩見岳の写真を見ると、左肩にパックリと口を開けた大きな切り傷のようになっているのが東池ノ沢である。現在も凄まじい速度で隆起を続けているという南アルプスの大地の力をまざまざと感じることができる場所だ。

やがて伏流していた流れが出てきて、沢は両岸から流れ込む沢山の小さな支流を合わせて少しずつ大きくなっていく。北俣との出合に近付くと水量も増え、多少渡渉に気を使うことになる。北俣の出合を過ぎると一旦流れは落ち着いて、前方に人工物が見えてくると小西俣との出合は近い。


中俣と小西俣の出合には西俣堰堤という大きな堰堤がある。ここには昔、東海パルプ株式会社(現:特種東海製紙)の人々が住まう、林業のための集落があったのだという。我々はここでかつての杣人の暮らしに思いを馳せる…なんてことはせず、ザックを放り投げ、歩いてきた中俣の向こうにひょっこり顔を出した蝙蝠岳を見上げて、のんびりと昼寝をした。


いつまでも寝ていても仕方がない。昼寝もそこそこにして先を行くことにしよう。ここからは小西俣を登っていく。小西俣もまた静謐で穏やかな流れだ。悪沢岳の北尾根に詰め上げる西小石沢の出合を見送り、度々出てくる瀞に潜むイワナの魚影に感嘆の声を上げながら進んでいく。上岳沢出合と瀬戸沢出合のちょうど中間あたりにある滝の高巻きが核心部だろうか。まあ、雪国の泥壁と異なり、一歩一歩砂地に確実に足を踏みしめていけば容易に先に進めるので、大したことはない。瀬戸沢の出合は落ち着いた雰囲気になっていて、しばし水浴びなどをしながら休憩した。



魚無沢を見送り、沢が内無沢と名前を変えたあたりで良さげな幕営適地を見繕い、今日の行程を打ち切った。夜中にタープをぼたぼたと叩く雨の音で目が覚めた。

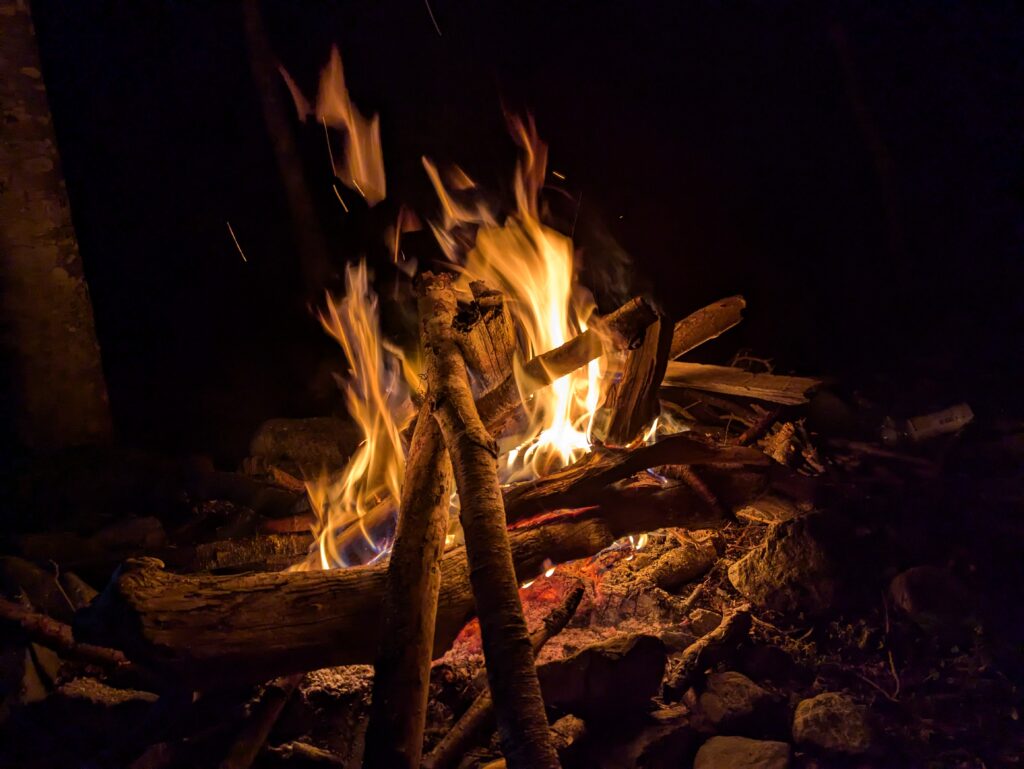
朝起きるとまだ雨が降っていた。幸い、沢は増水している様子はない。南アルプスは森林限界が高いので、山自体の保水能力も高いのだろう。土砂降りではないので、昨日と同じくらいの時間に出発することにした。今日は行程がそこそこ長いから、ダラダラしているわけにはいかないのだ。
岩にへばりつくハコネサンショウウオに朝の挨拶をしながら内無沢を進み、2050mの二俣を右に入って高山裏避難小屋を目指す。もう一方の沢には滝がかかっていた。


沢はだいぶ水量も減って源流部の雰囲気となり、緑に囲まれた小川のような沢を登って標高を上げていく。途中、沢の分岐を間違えたりもしたが問題なく進み、やがて水が少なくなって苔むした源頭部に辿り着く。高山裏避難小屋の水場を示すピンクテープが現れると登山道は近い。何てこともない整備された道ではあるが、水場から高山裏避難小屋に詰め上げる道が単純な急登で、もうすぐ小屋という安心感で気が緩んでいたのか、この山行で最もキツかった。


高山裏避難小屋に上がると霧雨がしとしと降っていた。とうに管理人は引き上げているようで、避難小屋状態の小屋に入って行動食を食べる。後から避難小屋に入ってきたおじさんと会話を交わし、情報交換をした後、「若いもんは歩けるやろ!」と言われたが、それは人によると思われる。
小屋から出て再び歩き始めるとすぐに雨が上がり、青空が姿を覗かせた。整備された登山道の歩きやすさに感動しながら、まずは小河内岳を目指す。時折伊那側がスッパリ切れ落ちた崩壊地になると、決まって僕たちは後ろを振り返り、雄大な荒川三山と赤石岳の姿を仰ぎ見ることになる。赤石山脈の盟主、赤石岳を護衛するように堂々と聳え立つ荒川三山がなんとも勇ましい。その向こうに、この山域の王者の風格を漂わせて、赤石岳が静かに鎮座する。南アルプスの山の雄大さに息を吞む。



板屋岳を越えると小河内岳の姿が見えた。まだまだ遠く見えて億劫になるが、もう足元を無理やり回転させるしかない。大日影山を越え、小ピークを2つ越えて小河内岳の登りに取り付く。右手に富士山が姿を現す。そうか、ここは南アルプスだった。沢の中にいたから、富士山のことなんて頭の中からスッポリと抜け落ちていたようだ。そうやって拍子抜けしている間に山頂に着いた。小河内岳のピークは南アのちょうど中間あたりにあるため、北部の山も、南部の山も、ぐるりと眺望できる素晴らしい展望台だ。



先輩がザックの中に隠し持っていた焼豚で塩分を補給して先を行く。ここからはおおよそ下り基調だ…そう思っていたのだが、なんだかんだまだ小ピークを2つ越えなければならない。100mくらい標高を落として、ヒイヒイ言いながら前小河内岳のピークに登り、また150mくらい標高を落として、烏帽子岳のピークに登る。烏帽子岳のピークから見る塩見岳は素晴らしく、ここまでの道程が一望できる。

ここからはもう下るのみだが、さすがに疲れてしまって、烏帽子岳からトボトボと力なく三伏峠に下りる。三伏峠小屋のランチタイムはとうに終わっていて、カレーにありつくことはできなかった。代わりに南アルプスの山々が描かれた暖簾を購入した。

三伏峠で出会ったトレラン装備のおじさんは、なんと鳥倉まで45分で駆け下るのだと言う。我々にはそんな芸当はできないので、マイペースに下っていくことにする。と言っても早く下りたい一心から、若干駆け足になったりもする。勢いのままに鳥倉まで駆け下って、林道の脇にザックを放り投げ、大の字になって曇り空を見上げた。あまり記憶にないが、どうやら2時間かからずに下ってきたようだ。

林道を無心で歩き、ゲートに着く頃には辺りはだいぶ暗くなっていた。時計を見ると18時過ぎ、久々の12時間行動だ。雨がパラついてきたので急いで荷物を車に押し込む。
帰りも長くて億劫だが、我々社会人は社会のしがらみから逃れられない。最後は女神様の暖かな微笑みを振り切って、日常に向かって再びアクセルを踏み込むのであった。
https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-7243799.html